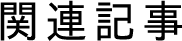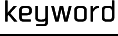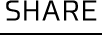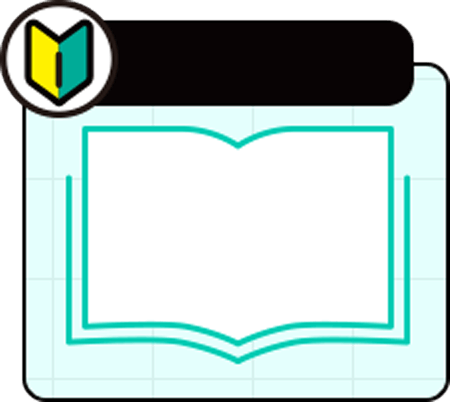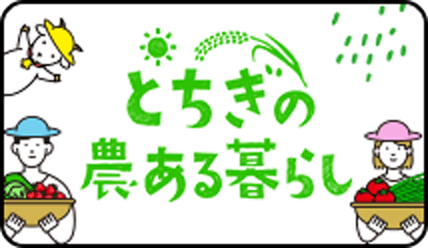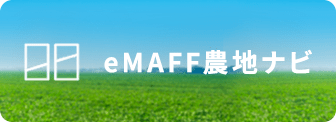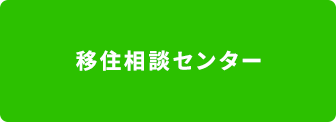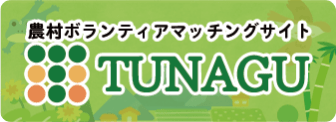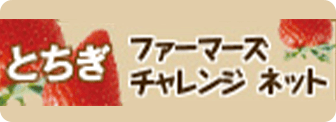高根沢町の概要

高根沢町は栃木県のほぼ中央に位置し、県庁所在地の宇都宮市の北東約12kmの場所にあります。町の東側には八溝山系の丘陵地帯、西側に鬼怒川があり、その中央部は平坦な土地。総面積の約60%を農地が占める、農業が盛んな土地です。
町内にJR東北本線と国道4号線が縦断し、東京駅まではJRの在来線と新幹線を利用して約50分。高速道路を利用し、車では約2時間です。
都心までのアクセスがいい立地でありながら、田畑が広がる清々しい風景にも恵まれています。
天皇ご一家が静養する御料牧場があることからも、落ち着いた美しい場所であることがわかります。

高根沢町の面積の約半分は水田。水張り時期は、一帯が鏡のように輝き、水稲が育つと青々とした力強さ、稲刈り時期には黄金の絨毯のような美しさを見せます。

建築家の隈研吾氏がデザインした近代的な建物、宝積寺(ほうしゃくじ)駅。2008年に国際的な鉄道デザインコンペティション「ブルネル賞」で奨励賞を受賞しました。
駅の東側には、隈氏が「光と風が通り抜けるイメージ」で設計した「ちょっ蔵広場」があり、大谷石が並ぶ広場として人気を集めています。

道の駅たかねざわ元気あっぷむらは、休憩所、情報発信などがあるほか、温泉なども併設。さらに、季節ごとに様々なイベントが開催されており、家族連れも多く訪れます。
高根沢町は、生活するのにも、子育てをするのにも便利です。町内の北東部と西部に市街地があり、スーパーやドラッグストア、衣料品店などが建ち並び、町内全域にさまざまなジャンルの飲食店がそろいます。

毎年秋になるとお祭りやイベントが開催されます。5,000~6,000人が集まる「たんたん祭り」は、10~11月に開催。稲刈り後の藁を集めて作った巨大なモニュメント「たんたんボッチ」に火を入れ、花火を打ち上げます。
自転車愛好家におすすめなのが「たかポタ」という自転車イベント。稲刈りが進む10月に、高根沢町の自然のなかで育てられた安心安全な秋の味覚を味わいながら、自転車でゆっくり走行するものです。
教育機関や子育て支援が充実!
町内には保育園、認定こども園などが10園、小学校が6校、中学校が2校と、教育機関が充実。第2子の保育料や、保育園の副食費の無償化、また、18歳までの子どもの保険適用の診療は所得制限なしで自己負担分を助成といった、子どものための厚い支援、助成が行われています。
妊娠子育てに関する悩みを保健師などの専門職に相談できる窓口「NIKO♡NIKO子育て相談室」や、さまざまなイベントが行われたり、親同士の交流を図ったりできる「子育て支援センターれんげそう」も、子育て世帯によく利用されています。
高根沢町の農業
高根沢町は、自然災害が少なく、肥沃な土地に恵まれています。古くから水稲栽培が盛んで、二条大麦、大豆、飼料作物も育てられています。
町内の農家は約1,500戸。地域の気候に合って販売力がある作物として、いちご、えだまめ、ねぎ、なす、トマト、春菊、たまねぎ、アスパラガスの8作物を町が選定し、園芸作物として推進しています。
栃木県のブランド米「とちぎの星」は、平成26年産から登場。平成27・29・30年産で日本穀物検定協会による食味ランキングで最高評価の「特A」を獲得しています。
令和元年の天皇皇位継承に伴う「大嘗祭」で使う新米を収穫する斎田に、高根沢町大谷地区の水田が選ばれ、高根沢町産の「とちぎの星」が献上されました。

地産地消の取り組みとして、町産のおいしいお米や、農産物を使用した「高根沢ちゃんぽん」・「高根沢焼ちゃんぽん」・「高根沢お米スイーツ・パン」の4品目を「高根沢ローカルグルメ」として認定し好評をいただいています。
新規就農者への支援事業
高根沢町では、園芸作物の生産振興と新規就農者の支援を目的に「園芸作物推進支援事業」を実施しています。この制度では、パイプハウスの整備に係る資材費用などについて、対象者ごとに補助率と上限額が設定されています。
◾︎パイプハウスの整備に係る資材費用の補助
- 認定新規就農者:補助率70%、上限200万円
- 新規就農者:補助率50%、上限150万円
- 新規作物導入(園芸作物を新たに導入する農業者):補助率50%、上限150万円
- 規模拡大(既存作物を拡大する農業者):補助率30%、上限100万円
認定新規就農者となることで、高い補助を受けられる仕組みとなっています。
高根沢町の「新規就農者育成研修事業」

高根沢町では、JAしおのやが設立した出資型農業法人「株式会社グリーンさくら」と連携し、新たに就農を目指す人を対象とした「新規就農者育成研修事業」を実施しています。この研修では、毎年10名程度を募集しており、4月から翌年3月までの1年間、JAしおのやの重点品目(7~8品目)の栽培技術、就農準備、制度資金、肥料・農薬、GAPなどが学べます。生産部会事業(目揃え会、現地検討会など)への参加、市場視察などもカリキュラムに含まれます。
受入研修生は74名(令和6年度末時点)の実績があり、JA管内4市町のうち高根沢町での就農は13名(親元就農3名、新規参入10名)となっています。
多品目から選べる「間口の広さ」が特徴!
「新規就農者育成研修事業」の研修作物は、いちご、アスパラガス、なすをはじめ、幅広い品目が対象となっています。就農に向けて品目を決めかねている人でも、研修を通して実際に様々な品目の農作業を体験しながら決めていける「間口の広さ」が特徴です。
また、研修期間中は毎月10万円程度の手当が支給され、給付を受けながら農業の基礎を学ぶことができます。
(※研修中に毎月もらえる10万円の手当は、国の就農準備資金と合わせて受け取ることはできません)
もちろん、研修終了後の経営開始に向けた資金活用についても相談可能です。
[研修期間]
4月1日~翌年3月31日 ※期間延長あり
[募集期間]
研修開始前年の9月1日~
[応募資格]
次の全てを満たす満年齢が18歳以上、原則45歳未満の方
(1)心身ともに健康であること
(2)農業に対する固い意志と意欲がある農業後継者や新規就農希望者
(3)研修後もJAしおのや管内で居住し、一定期間(10年)就農できる方
[選考審査]
書類選考・面接審査
栃木県で農業を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ
研修利用者インタビュー 大森俊太郎さん

父が営む「大森果樹園」で3年前から農業を始めた大森俊太郎さん。
高校進学時には農業系高校も検討しましたが、最終的には工業系の高校へ進学。「まずは世間を見てから」と助言を受け、自動車会社に就職しました。

「いつかは農業をやるだろう」という意識は常にありました。両親が引退の年齢に近づいてきたこともあり、「就農するなら今だ」と動き出しました。
10年ほど会社員として働いた経験が、今の農業に役立っています。振り返れば、学校を卒業してすぐに農家になるのではなく、社会で経験を積んでから就農してよかったと思っています。
3代目農家としてのスタート

大森さん一家は祖父の代から農業を営んでいます。祖父はたばこなどを栽培し、父の代から果樹園としてりんごといちごを栽培するようになりました。
現在は、父の元で従業員として働き、りんごとブルーベリーは両親が、大森さんがいちごを栽培しています。

両親のもとでの就農だったため、外部研修を経ずに始めることも可能でした。父が営んできた農園は順調で、技術的にも大きな不安はありませんでした。
それでも就農後を見据え、地域の関係者とつながりを持ち、新しい情報を得るために「グリーンさくら」での研修を受けることにしました。
1年間はグリーンさくらの研修と父親の畑の手伝いを半々

グリーンさくらでは、1年間の研修カリキュラムが組まれていますが、個人の事情に合わせて研修の内容を選べるようになっています。
大森さんは、親元就農が決まっていたので、研修を受けながら、休みの日には両親の畑の手伝いをしていました。

いちご栽培は、1年で1作しかできないのですが、グリーンさくらと両親の手伝いをしていたので、2年分の経験が積めた感覚です。
いちごだけでなく、アスパラガスをはじめさまざまな作物の肥料管理や病害虫対策、作業のタイミングなどをグリーンさくらで学びました。
ある程度はいちご栽培の知識があったので、研修先でも作業を任せてもらうことや「こうやってみたい」という考えを尊重してもらうこともありました。
いちごの品質を守るために欠かせない「蜂」の管理を学ぶ

研修では、ほかの農家の見学や鳥獣害対策の勉強など、さまざまなことを学びました。特に印象に残っているのが、蜂の扱いについてです。

所属している4Hクラブ(※)に出席の誘いがあったセミナーの中に、養蜂の専門家に来ていただき、蜂が減少している現状やその対策について教わるものがありました。猛暑の影響で全国的に蜂不足が深刻化していますが、巣の設置場所を工夫することで被害を軽減できるそうです。
いちごは受粉が大事で、蜂の働き次第で実の出来が変わるんです。だから蜂の管理は本当に大切だと感じています。
(※)4Hクラブ(農業青年クラブ)は
20~30代前半の若い農家が中心になって、経営や技術の解決方法を検討するプロジェクトや地域ボランティアなどを行っている組織です。
現在、日本全国に約630クラブ、約9,000人のクラブ員が活動しています。
栽培方法はマニュアルを基本にさまざまな工夫も

大森果樹園で育てているいちごは「とちあいか」。2019年秋から一般的に流通し始めた栃木県オリジナルの品種です。
「とちあいか」には栃木県が作成した栽培マニュアルがあり、基本的なところはおさえながら、ほかの農家にも話を聞いて肥料のやり方に工夫をくわえています。
農業振興事務所やいちご研究所の勉強会にも参加し、肥培管理や病害対策を学びました。
さらに、高根沢町のスマート農業推進事業を活用し、環境モニタリング機器も購入しました。
その甲斐あって、導入1年目、2年目も収量を導入前の1.5倍程度に増やすことができました。
大森さんのこだわりはほかにもあります。それは、農薬をできるだけ減らす方針です。いちごにつきやすい害虫の天敵を利用して減農薬に取り組んでいます。

農業を営むうえで、大切なのは情報です。とちあいかが出てまだ6年で、毎年作り方が更新していきます。気温も上がってきていますし、それに合わせる方法など新しい情報を吸収する必要があります。
今後は経営継承する予定

現在は父が経営する会社で従業員として働いていますが、近い将来、経営を継承する予定です。その日のために、両親の手を借りなくて済むように設備を増やしているところです。
親元就農したおかげで就農時の費用面をはじめ、メリットはたくさんありました。でも、やはり家族で同じ組織で働く難しさもあるのだといいます。

研修で学んだことと、両親がやってきた昔ながらのやり方が合わないと感じることがあります。でも、それぞれが違う方向性でやろうとするとうまくいきません。
お互いに、気がついたことがあれば言いますが、言い過ぎないようにも心がけています。
今、りんごを両親、いちごは自分と担当分けしていますが、こんなふうに担当分けするのも解決方法の1つかなと思います。
就農後、ハウスを2棟増やし、肥料のやり方など栽培に工夫をして順調に売り上げを伸ばしているという大森さん。最後に、これから就農を目指す人へのメッセージをいただきました。

良質な情報を得るために、農家や業者やJA及び県・市町・行政など、いろいろなところとコミュニケーションをとるといいと思います。自分だけで考えていても解決しないことが多いので、アンテナを広げてたくさんの人と付き合うことをおすすめします。
さいごに
大森さんは、父の元で農業を始め、スタート時から後押しとなる条件が整っていました。
それでもその状況に頼ることなく、自ら最新の技術を学び、地域の関係者や取引先とも積極的に関わりながら歩みを進めています。取材を通じて、大森さんがこれからさらに成長していく姿が思い描けました。
INFORMATION

大森果樹園
りんご栽培から始まり、現在はブルーベリーといちごも栽培。自然環境、食の安全性を常に第一に考えてこだわりの果実を栽培している。
りんご(シナノゴールド、秋映、アルプス乙女、シナノスイート、名月、ふじ)は約500本、ブルーベリーは10種類約500本、いちご(とちあいか)は約34a栽培。
https://www.instagram.com/ohmorikajuen_ofg/
農地情報
農地のあっせんや賃貸借等のご相談は、高根沢町産業課及び農業委員会事務局で随時受け付けています。
空き家情報
高根沢町では「空き家バンク制度」を設けており、高根沢町のホームページにて物件情報を掲載しています。また、登録されている空き家を購入し改修した場合には、改修費用の一部を補助する支援制度があります。
相談窓口
【就農相談】
高根沢町産業課 TEL:028-675-8104
【農地情報】
高根沢町産業課 TEL:028-675-8104
高根沢町農業委員会事務局 TEL:028-675-8108
【空き家情報】
高根沢町都市整備課 TEL:028-675-8107
【空き家の改修】
高根沢町地域安全課 TEL:028-675-8110
【移住・定住】
高根沢町企画課 TEL:028-675-8102
 TOCHINO-トチノ-
TOCHINO-トチノ-