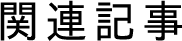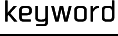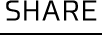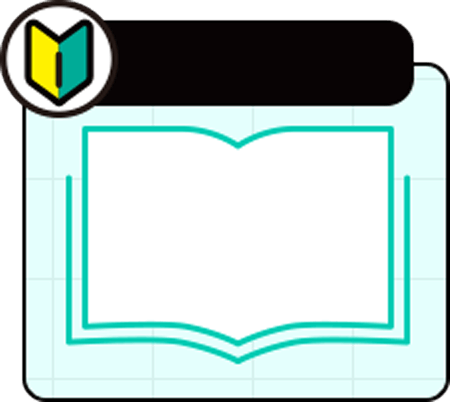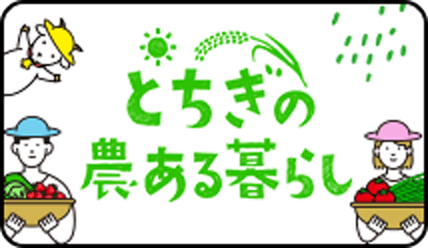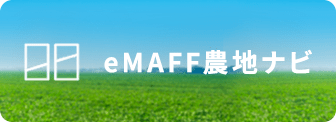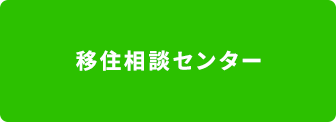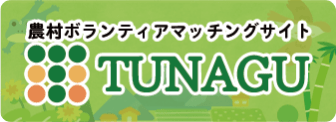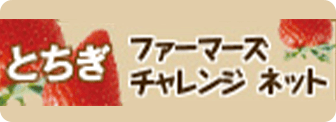さくら市の概要

さくら市は宇都宮市に隣接し、東京都心へは鉄道で約70分と好アクセス。市の中心から高速道路ICまでも車で約15分と便利です。観光地への距離も程よく、日光や益子までは車で約45分、那須へも約40分です。
さくら市は旧氏家町と旧喜連川町の合併によって誕生しました。
旧氏家町はショッピングモールやドラッグストアなどの商業施設が多く利便性に優れ、旧喜連川町は自然豊かで日本の原風景が残る地域です。こうした両面を併せ持つことから、市は「ちょうどいい!さくら市」と掲げています。
桜の名所も市内各地にあり、春には多くの人でにぎわいます。なかでも「氏家ゆうゆうパーク」は、旧氏家町の町制100周年事業として鬼怒川河川敷に整備された公園の愛称です。全長約1.5kmの桜づつみには約500本のソメイヨシノが植えられ、満開の時期には見事な景観を楽しめます。ここで毎年開かれる桜まつりでは屋台や夜間ライトアップも行われ、地域の人々や市外からの来訪者に広く親しまれています。

夏の人気スポットは「道の駅きつれがわ」です。隣接する川沿いの水辺公園では子どもたちが水遊びを楽しめ、アウトドア派にはバーベキュー場やキャンプ場が整備されており、自然の中で思い切り遊ぶことができます。周辺には「日本三大美肌の湯」として知られる喜連川温泉もあり、家族連れから観光客まで幅広く親しまれています。
さらに、市内ではフットゴルフも盛んです。サッカーボールを使い、ゴルフ場に設けられた18ホールまたは9ホールのコースをゴルフとほぼ同じルールで楽しむスポーツで、近年はプロチームも誕生するなど注目を集めています。

秋の見どころは、創建960年の歴史を持つ今宮神社の大いちょうです。市の天然記念物に指定されており、境内を代表する存在です。黄葉の時期には葉が一面に色づき、訪れる人々を楽しませます。

11月には喜連川の花火大会が開催されます。打ち上げ場所が低く、堤防に反響して大きな音が響くのが特徴で、近くで観覧できる点も魅力です。

さくら市は「年少人口比率」が6年連続で県内1位、「合計特殊出生率」も県内1位で、子どもの割合が多い地域です。子どもの医療費助成も県内で早い時期から始まり、子育て世代を支えてきました。
保育施設や放課後児童クラブは待機児童ゼロを実現しており、安心して子育てができます。さらに「子育て世代包括支援センター」では、子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できます。市内の小中学校には冷房が整備され、体育館にも導入されているため、子どもたちが快適に過ごせる環境が整っています。
さくら市の農業

さくら市の面積のうち、田畑が占める割合は約43%。関東平野の北端に広がる平野部では、米や麦、大豆が栽培され、地域の基幹作物となっています。川や地下水が豊富で水資源に恵まれているため、多様な作物に挑戦できるのも特徴です。近年は施設園芸も増え、トマトやいちご、にら、なすなどの生産が拡大しています。
丘陵地では、りんごやいも、そばに加え、なすも多く育てられています。井戸を掘って水を確保し、いちごやにらに取り組む農家の姿も見られます。なかでも温泉熱を利用して栽培する「喜連川温泉なす」は、やわらかくみずみずしい食感が評判で、地域の特産品として定着しました。
市内には直売所が点在し、新規就農者にとっても販売の場を確保しやすい環境が整っています。さらに農産物のふるさと納税にも力を入れており、返礼品として出品すれば新たな販路につなげることも可能です。
さくら市独自の農業支援制度も充実!
さくら市は、農業者を支えるために、市独自の補助制度を整備しています。就農初期の設備投資から規模拡大、スマート農業への挑戦まで幅広く活用できるのが特徴です。
- 施設整備補助:振興作物(いちご・にら等)のハウス新設や拡張に利用可。規模拡大は2a以上が条件、補助上限200万円。
- 新規作物導入補助:新たに振興作物を導入する際の種子・種苗費を助成(継続作付3年以上が条件)。上限20万円。
- 農業機械導入補助:20万円以上の機械・設備が対象。規模拡大は施設2a以上、露地30a以上などの条件あり。個人は100〜150万円、団体は200万円まで補助。
- スマート農業機器補助:スマート農業技術カタログなどに掲載された20万円以上の機器が対象。上限200万円。
さくら市の「新規就農者育成研修事業」

さくら市では、JAしおのやが設立した出資型農業生産法人「株式会社グリーンさくら」と連携し、新たに就農を目指す人を対象とした「新規就農者育成研修事業」を実施しています。
この研修では、毎年10名程度を募集しており、4月から翌年3月までの1年間、JAしおのやの重点品目(7~8品目)の栽培技術、就農準備、制度資金、肥料・農薬、GAPなどを学べます。生産部会事業(目揃え会、現地検討会など)への参加、市場視察などもカリキュラムに含まれます。
新規就農者育成研修事業を経て、さくら市での就農した人は28名(親元就農6名、新規参入22名)となっています。
多品目から選べる「間口の広さ」が特徴!
「新規就農者育成研修事業」の研修作目は、いちご、アスパラガス、なすをはじめ、幅広い品目が対象となっています。就農に向けて作物を決めかねている人でも、研修を通して実際に様々な品目の農作業を体験しながら決めていける「間口の広さ」が特徴です。
また、研修期間中は毎月10万円程度の手当が支給され、給付を受けながら農業の基礎を学ぶことができます。もちろん、研修終了後の経営開始に向けた資金活用についても相談可能です。
[研修期間]
4月1日~翌年3月31日 ※期間延長あり
[募集期間]
研修開始前年の9月1日~
[応募資格]
次の全てを満たす満年齢が18歳以上、原則45歳未満の方
(1)心身ともに健康であること
(2)農業に対する固い意志と意欲がある農業後継者や新規就農希望者
(3)研修後もJAしおのや管内で居住し、一定期間(10年)就農できる方
[選考審査]
書類選考・面接審査
研修制度利用者インタビュー おやまだ農園 小山田和弘さん

小山田さんは栃木県矢板市の出身です。保育士として勤務していましたが、次第に自分には合っていないのではと感じ、将来について考えるようになりました。
そのとき思い出したのが、子どものころに両親と訪れた北海道での体験です。農業に触れた記憶が心に残っており、その思いをきっかけに北海道のじゃがいも農家に就職しました。約6年間働いた後、職場の体制が変わったことをきっかけに進路を見直し、故郷へ戻る決心をしました。

両親からも、そろそろ栃木に帰ってこないかといわれていましたし、ちょうど、平成から令和に変わるときだったので、いいタイミングだと思い、Uターンすることにしたんです。
栃木県と市町とで開催している新規就農者向けのフェアに参加したところ、グリーンさくらの研修を紹介してもらいました。
グリーンさくらでの研修は野菜から花きまで

1年間の研修では、いちご、メロン、たまねぎ、オクラ、キャベツ、にら、菊、りんどうなどを育てました。
県やJAなどの農業団体が実施する座学のほか、外部団体による講習にも参加でき、栽培管理や農薬の扱い、経営に関する知識を学べました。

グリーンさくらでの研修は、ほ場での実習に加え、専門性を高めるために多方面から学ぶ機会が設けられていました。病害虫防除や雑草対策に関する農薬の適正使用については、「緑の安全推進協会」から講師を招いて学ぶ場もありました。ほ場での実習では、1年を通して作業の適切なタイミングを理解できたことが大きな収穫でした。
研修のなかでいちご農家になろうと決意

グリーンさくらの研修では、まだ栽培作物を決めていない人が、さまざまな野菜や果物、花きを育てながら、自分に合った作物を見極めていくことができます。小山田さんも当初は迷っていましたが、研修の中頃から「いちごを育てよう」と思うようになったといいます。

いちごは栃木県を代表する作物であり、自分も育てていきたいと思うようになりました。また、収益性の高さを感じたことも、選んだ理由のひとつです。
順調に進み、補助金が途中で必要なくなるほど

農地は親戚の伝手で地主を紹介してもらい、離農する方から借り受けることができました。
就農時には、「認定新規就農者制度」を活用しました。この制度により当時、経営開始から年間最大150万円(最長5年間)の支援(所得に応じて給付額は変動)を受けられる農業次世代人材投資事業(経営開始型)の支給が認められました。(現在は3年間に変更)。

経営は順調に進み、収入が制度の基準を超えたことで、5年目には補助金に頼らなくてもやっていけるようになったんです。就農後はハクビシンの被害こそありましたが、それ以外に大きなトラブルはなく、直近ではいちごの収穫量も約8トンにまで増えて、年々着実に伸びているんですよ。
出荷先はJAが5割、直売所が6店舗で3割です。さらにふるさと納税(11月下旬〜3月下旬)の返礼品としても好評で、リピーターになってくれる方もだんだん増えてきたといいます。

ゴールデンウィークを過ぎると、どうしてもいちごの売れ行きが落ちてしまうので、就農5年目からは冷凍庫を導入して、冷凍いちごの生産にも取り組むようになったんですよ。夏場は需要が高く、近隣の人や知り合いが買いに来てくれることも増えています。
研修生の受け入れも
経営が軌道にのり、研修生も受け入れるようになりました。就農を希望する2人が、パートとして働きながら研修をし、就農しました。そこには「同じ地域でいちごを育てる仲間を増やしたい」という小山田さんの思いがあります。

農業は自然と向き合い、長い時間と努力を必要とする、やりがいのある仕事です。研修を通じて学ぶことは、あなたの未来の基礎となります。大切なのは、挑戦する心と、学び続ける姿勢だと思います。あなたの情熱と努力が素晴らしい農業人生を築く原動力となるでしょう。
みなさんの挑戦が豊かな自然と地域にとって新しい風となることを願っています。共に成長し、夢を叶えていきましょう。
INFORMATION

おやまだ農園
とちあいかを栽培するいちご農園を小山田さんと両親の3人で経営。ほ場は現在28a。繁忙期には2〜3人、収穫期には7〜8人のパートを入れて作業を行う。出荷先はJAが5割、直売所が6店舗で3割、ふるさと納税にも納品しており、返礼品として好評でリピーターも増えている。
まとめ
小山田さんは就農から3〜4年で経営を安定させ、順調に軌道に乗せてきました。研修生を受け入れることについて「まだ自分も学ぶことが多い」と謙遜しますが、研修や自分の畑で積み重ねた技術を生かし、着実に成果を上げています。これからも研修生を迎えながら、同じ地域でいちごを育てる仲間を少しずつ増やしていきたいと話してくれました。
就農に関する相談は、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ
地域おこし協力隊から新規就農をめざす道も!
さくら市では、任期後に新規就農を目指す地域おこし協力隊を募集しています。農家での作業支援や農業研修に加え、地域農業者を支える「農援隊」としての活動や、直売イベントでのPR、SNSを活用した情報発信など、幅広い経験を積むことができます。こうした取り組みを通じて栽培技術や経営の知識を学び、地域とのつながりを築きながら就農への準備を進めます。
これまでに地域おこし協力隊から移住・就農につながった事例もあり、地域の担い手づくりに貢献しています。現在は、農業の実践と発信を組み合わせた新しい形の募集も行われており、多様なチャレンジの場が用意されています。
農地情報
農地のあっせん制度
高齢で離農、相続した農地を耕作できない、後継者がいないので農地を貸したいといった人から、新規就農者などへの土地のあっせんを行っています。
農地バンク
低利用農地・遊休農地の売買や賃借希望等の情報を収集し、新規就農希望者や経営拡大したい農家などに、農地情報の提供を行っています。
空き家情報
空き家の有効活用と移住希望者への移住促進策として、空き家・空き店舗バンク事業を実施しています。
相談窓口
【移住定住について】
さくら市 総合政策課 政策推進室 移住定住推進係 028-681-1113
【農地について】
さくら市 農業委員会事務局 農地調整係 028-681-1124
【就農について】
さくら市 農政課 農政係 028-681-1117
 TOCHINO-トチノ-
TOCHINO-トチノ-