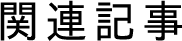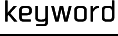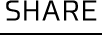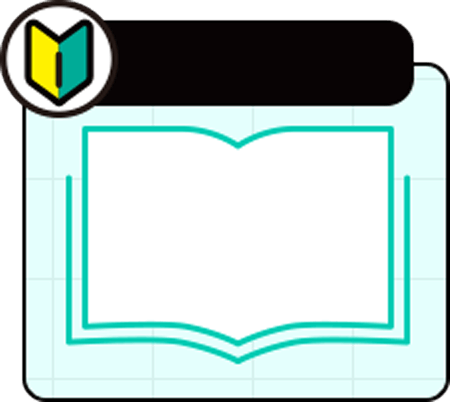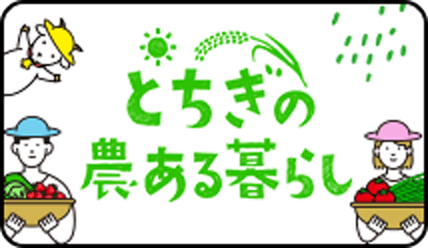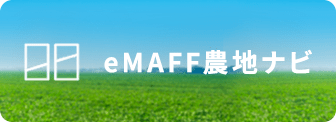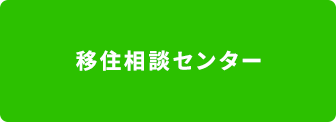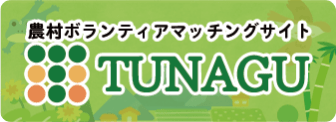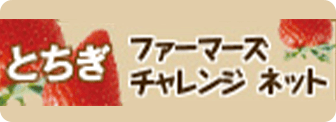野木町の概要

野木町は栃木県の最南端に位置する、県内で最も面積の小さい自治体です。東京から60km圏、宇都宮市からは40km圏にあり、小山市と栃木市に隣接しています。
東京都心へはJRで直通約60分とアクセスも良好。交通の利便性に加えて、0~18歳を対象にした医療費助成などの子育て支援も整っており、自然環境の中で子育てをしながら、都内へ通勤するライフスタイルを選ぶ人もいます。

野木町は益子町、上三川町と共同で「ひまわりサミット」を運営しています。夏には毎年「ひまわりフェスティバル」を開催。たくさんの模擬店が並び、なかでも4Hクラブ(青少年クラブ協議会)が育てたとうもろこしで作る焼きとうもろこしは例年大人気です。
広々としたひまわり畑は、フェスティバル以外の時期でもフォトスポットとして紹介され、撮影目的で訪れる観光客の姿も見られる人気の場所となっています。


野木町の古い歴史を物語る野木神社は、およそ1600年前、仁徳天皇の時代に建立されたとされ、坂上田村麻呂が延暦21年(802年)にこの神社に詣でて勝どきをあげたという伝説があります。現在の社殿は文政2年(1819年)に再建されたものです。
境内の大イチョウは栃木県の名木100選に選ばれており、垂れ下がる気根(植物の茎や幹から空気中に出る根)が乳房に見立てられ、母乳の出に悩む人々の信仰の対象となってきました。
また、この神社はフクロウが営巣することでも知られ、春になると観察や撮影を楽しもうと多くの人が訪れる場所になっています。

町の名所「野木町煉瓦窯」(旧下野煉化製造会社煉瓦窯)は赤煉瓦の製造に用いられていた設備で、国の重要文化財に指定されています。
煉瓦窯は、環状に区画を並べて順番に焼成していく「ホフマン式輪窯」が採用されており、連続的に煉瓦を生産できる仕組みになっています。国内に現存する同式の窯はわずか4基のみで、ここで焼かれた煉瓦は明治から昭和にかけて、各地の建築物や鉄道の資材として広く利用されました。
この場所では、毎年秋に「野木町煉瓦窯秋フェスタ」が開催され、ジャズの演奏会、ポニー乗馬体験、燻製料理や煉瓦粘土のワークショップなど、さまざまなイベントが行われます。

幅広い子育て支援制度が充実
野木町は、妊産婦から小学生までを対象にした支援や、不妊治療への助成など、幅広い子育て支援を実施しています。具体的には、以下のような制度があります。
- 出産祝い金:第1子・第2子は2万円、第3子以降は10万円を支給
- チャイルドシート購入費補助:購入費用(消費税込)の3分の1を補助(1台につき上限1万円)
- 第3子以降保育料免除:条件に応じて第3子以降の保育料を免除
- 第3子以降入学祝い金:小学校入学時5万円、中学校入学時5万円を支給(平成27年度から開始)
- 不妊治療支援事業:体外受精などにかかる治療費の一部を助成
また、子育て支援センター(げんきっこくらぶ)が設けられており、保育士や子育て経験者に育児の不安や悩みを相談できるほか、親子で参加できる遊びや育児講座なども提供しています。
野木町の農業

野木町の総面積の3,027haのうち、田畑が占める面積は約1,160ha。内訳は水田が約790ha、畑が約370haです。野木町は農業が盛んな地域で、主な農産物は米麦と、いちごやトマトなどの施設野菜、レタス、ブロッコリー、白菜といった露地野菜などが栽培されています。
いちご農家が急増
近年、新規就農した若い世代にはいちご栽培が人気で、徐々にいちご農家が増えつつあります。
現在、20〜30代の認定新規就農者が6名、令和8年度に2名が新規就農予定で現在準備中です。
県全体でいちごに力を入れていることもその理由の一つですが、親世代がほかの作物を育てていた農家の二代目、三代目で新たにいちごを始めるという人も増えています。
一部の地域は有機農業指定地域に
野木町では、1990年代から有機栽培が行われています。2015年に有機農業を行うグループが「野木町有機農業研究会」を発足。2024年には農業者、商工会、JA、行政などで構成する「野木町グリーン農業推進協議会」を設立して、環境に配慮した農業を推進しています。若林、佐川野、川田地区が有機農業の特定区域に指定され、有機農業の拠点となっています。
いちご農家を育成する研修制度「JAおやま新規就農塾」と提携
野木町はJAおやまをはじめ、小山市、下野市と提携し、令和4年に「JAおやま新規就農塾推進協議会」を設立しました。令和5年からは、「JAおやま新規就農塾」で、いちごの研修生の受入を開始しています。この塾では、とちぎ農業未来塾(栃木県農業大学校)で基礎知識を学ぶだけでなく、JA管内の先進的ないちご農家のもとで栽培技術の研修を行い、「いちご王国とちぎ」を支えるいちご農家を育成するカリキュラムが用意されています。
【JAおやま新規就農塾】
[研修内容]
いちご農家での実技研修(実際の農作業を通じての研修)
就農準備校「とちぎ農業未来塾」の受講(座学・実習による農業技術・農業経営等の研修)
[研修期間]
1年間(毎年4~3月)
[研修費用]
・いちご農家での実技研修は受講料無料
※その他、現地作業等に必要な備品等については自己負担
・就農準備校「とちぎ農業未来塾」受講料5万円(自己負担)
[対象]
●18~48歳
●研修修了後、JAおやま管内でいちご経営を開始すること
●JAおやまの組合員になること
●JAおやまいちご部会に加入すること
[選考方法]
申込書を提出後、書類審査と面接審査の上決定
[募集人数]
若干名
野木町でいちご栽培を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ
新規就農者インタビュー|県外出身の同級生3人でいちごを共同経営

柿沼修平さん・小町竜暉さん・布井佑紀さんは友人同士で、2024年に共同でいちご経営を始めました。
柿沼さんと小町さんは高校の同級生、小町さんと布井さんは大学の同級生で、全員20代。若い3人が農業を始めようと思ったきっかけはそれぞれに異なりますが、一緒にやろうという意気込みは一緒でした。
現在、出荷名義は柿沼さんになっていますが、三人が対等な立場で経営しています。
柿沼修平さん(埼玉県白岡市出身)

祖父が野木町の農家で、子どもの頃からいずれは農業に関わる仕事に携わりたいという気持ちを持っていました。高校時代、小町さんと「いつか農業をやりたい」という話をしていたんです。
学校を卒業後、企業に就職して3年間勤務したのですが、小町さんから農業をやらないかと誘われたとき、もとから抱いていた気持ちとつながって始めることにしました。
小町竜暉さん(埼玉県さいたま市出身)

新卒で入った会社でスマート農業を推進する部署が立ち上がり、その部署に配属されました。
そこで農業についていろいろ学びました。高校生のときから自分で経営したいという夢があって、農業ならチャンスがあるかもしれないと思うようになって、二人に声をかけたんです。
布井佑紀さん(神奈川県大磯町出身)

兄が二人いて、いちばん上の兄が会社員を辞めて農家になりました。その影響を受け、大学時代、僕も農業をやってみたいという話をしていたのですが、それを小町さんが覚えていて声をかけてくれました。
やるなら今だ、と思って飛び込むことにしました。
幅広い知識を得るために研修は3人別のところで

小町さんは栃木県農業大学校いちご学科で2年間学び、柿沼さんは小山市の農家で2年間働きながら研修、布井さんは神奈川県の農園でアルバイト兼研修を受けました。
それぞれに違う場所で学ぶことで、より広い見識が得られるのではないかという目論見からでした。

それぞれに違う方法を学んできているので、時には議論になることがあります。
でも経営をしていくうえで、それは必然的なことです。誰かひとりが引っ張りすぎてもよくないですから。

技術のベースは、小町さんが農業大学校で学んだ内容です。小町さんが学んできたことにそれぞれ学んだことを突き合わせていく感じです。
技術面で大きくもめることはありません。

農業大学校のいちご学科では、本当にすごい人の講義も受けましたし、体系的に学んできたので、二人に対しても「こういう理由があるからこうしよう」と説明して納得してもらっています。
うまくいちごを作っていこうという思いは同じなので、お互いに自我が出てぶつかるということはありません。
就農準備に3年かけ、資金は共同で貯めた

米やなすを育てていた、柿沼さんの祖父が離農することになり、農地はそこを引き継ぎました。栽培に必要な井戸もあったため、いちごには最適な土地でした。
トラクターや軽トラックも祖父のものをそのまま利用し、ハウスはほかの農家で不要になったものを譲ってもらって3人で組み立てました。
新たに購入したものはいちごを保存する予冷庫と畝上げ機程度だったといいます。

2年間の研修で給与もいただいていたので、それで生活費と就農の準備にあてる費用を貯めていきました。100万円くらいはみんなで頑張って貯めようという話をしていました。
経営開始資金(※)の交付も受け、その他、青年等就農資金(※)から借り入れを行いました。野木町の産業振興課から手厚くサポートしていただいて、各種資金を得ることができました。

農業大学校に通っていたので、就農準備資金(※)を申請して、それで生活することができました。
就農準備には3年かけたので、やれるだけのことはやったと思います。
(※)就農準備資金・就農開始資金・青年等就農資金
就農準備資金・就農開始資金は、次世代を担う農業者となることを志向する49歳以下の者に対し、就農準備段階や経営開始時の早期の経営確立を支援する資金を交付。
青年等就農資金は、新たに農業経営を営む青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける制度。

いちばん入手に苦労したのがハウスです。
小町さんが農大に通っていたときのつてで農家を紹介してもらい、譲ってもらえましたが、それがなかったらかなりきつかったと思います。
そのほか、小さい道具も小町さんを通して農家から譲り受けることができて、かなりコストカットにつながりました。
いかにお金をかけずに設備を確保できるか|コミュニティ作りが大切

野木町では、いちごで新規就農する若い世代が増えており、地域のコミュニティへの参加も活発です。3人は、4Hクラブ(青少年クラブ協議会)にも所属し、地元の若い農業者と積極的に交流を行っています。

4Hクラブには13~14人ぐらい所属しています。町内のイベント「ひまわりフェスティバル」に出店したり、定例会で新しい事業をいろいろ考えたりしています。その裏でもたくさんの交流があり、情報共有しています。仲間がいっぱいいればいるほど助かりますね。

4Hクラブのメンバーにもお世話になっています。農業は孤独を感じやすい仕事なので、周りに気軽に話せる人がいるのは、精神的な支えになっています。

新規就農者はなかなか地元になじみにくいと感じるものですが、4Hクラブで親元就農している人とつながったおかげで、地元とのコネクションもできました。
サークルみたいな感じで、日頃の作業の息抜きにもなっています。
2年後には栽培面積を拡大し、売上6,000万円を目標に

就農当初は栽培面積23aからスタートし、現在のほ場は30a。さらに、高設ベンチが整備された20aの連棟ハウスを借りられることになり、2年後の収穫に向け準備が進められています。規模拡大後の売上目標について聞いてみました。

10aあたり、1,000万円が目標だと言われているので、50aなら5,000万円はいくはずです。
目標が5,000万円だと下振れしてしまうから、5,555万円、いや目標は6,000万円でしょうか。

就農開始時ならこわいもの知らずで6,000万円といえたと思うんですけれど、リアルな状況を考えると、控えめになってしまいますね(笑)

スマート農業の部署にいた経験から「稼げる農家になりたい」と思っています。いちごは施設園芸で機械化しやすく、IT化・自動化との相性もいいです。今後も効率化に投資し、所得を上げて「農業で稼げる」ことを証明したいですね。
ただし、最初から自動化に頼りすぎるのは避けたいです。まずは自分たちの感覚で技術を身につけ、その上で次のステップに進みたいと考えています。
農業を職業の選択肢の一つとして考えてほしい
最後に、これから農業を目指したいと考えている人に向けてのメッセージを、代表して布井さんに語っていただきました。

会社員として働いていて、自分には合わないという悩みをもつ人もいると思うのですが、そんなときの選択肢の一つに農業を考えてみては、と思います。農業は、日本を支える職ですから。
今は、農業に偏見をもつ人がいるような時代ではないので、勇気を出して飛び込んでみてください。
さいごに
友人同士で協力して就農するというのは珍しいケースですが、3人の明るい顔は大きな可能性を感じさせてくれました。
誰にでもできることではないかもしれませんが、一人での就農よりも大きな規模で始められるメリットもあり、新しい就農の形を見せてもらえました。
最初の1年は小さな失敗もあったとのことですが、順調に進んでいる様子。今後の3人の姿が楽しみです。
野木町でいちご栽培を始めるなら、栃木県農業振興公社のワンストップ窓口へ
INFORMATION

柿沼修平さん 小町竜暉さん 布井佑紀さん
かきぬま・しゅうへい こまち・りゅうき ぬのい・ゆうき|30aのほ場でいちご栽培を行う。2024年4月に新規就農し、11月初出荷。外部向けの代表者は柿沼さんになっているが、実際には3人で対等な立場で経営を行う。2027年には20aの高設栽培ハウスを増設予定。
農地情報
農業委員会では相談窓口を設けており、各地域を担当する委員が相談に応じています。地域の農家に直接相談することで、現場の実情を確認することもできます。
空き家情報
「野木町空き家バンク」では利用可能な空き家の登録情報が公開されています。売りたい・貸したい方と、買いたい・借りたい方とのマッチングができます。
相談窓口
【新規就農について】
野木町農業委員会 TEL 0280-57-4109
【新規就農支援について】
野木町 産業建設部 産業振興課 農業振興係 TEL 0280-57-4151
【移住について】
野木町 総合政策部 政策課 未来創造係 移住定住促進班 TEL 0280-57-4178
 TOCHINO-トチノ-
TOCHINO-トチノ-