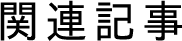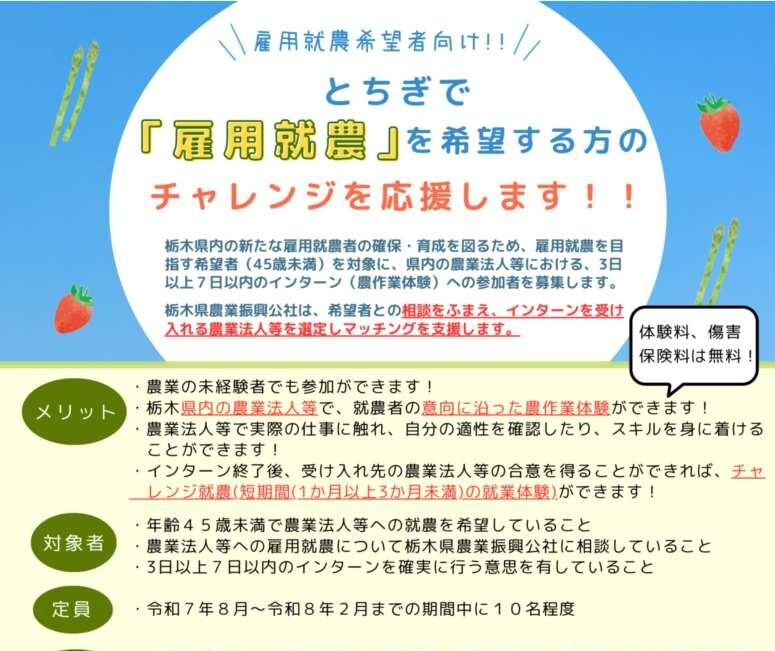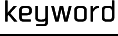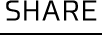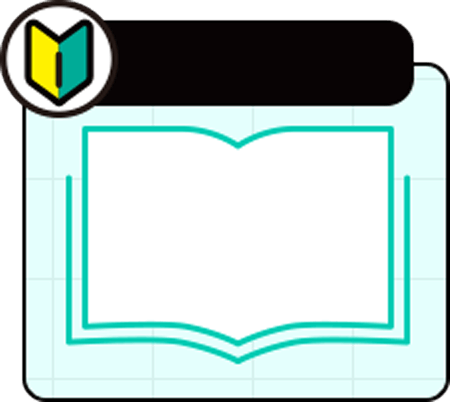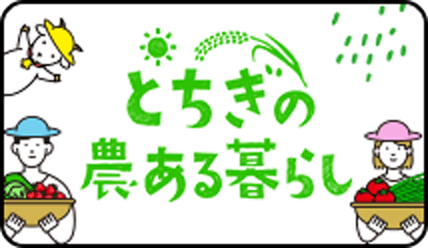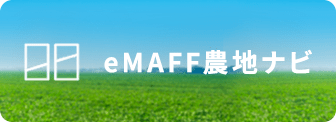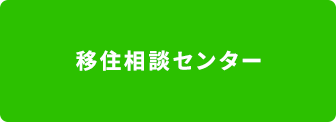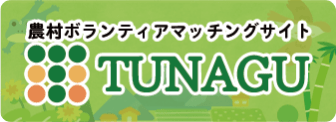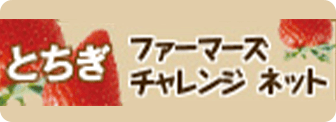INFORMATION

とちぎ農ある暮らし体験交流
2025年8月23日(土)9:45~16:00、宇都宮市の道の駅うつのみやろまんちっく村で開催。
農ある暮らしの先輩実践者との交流や農業体験、お菓子作り教室を通して、農ある暮らしを考えるイベント。当日は、栃木県内外から13名が参加し、4名の先輩実践者と交流しました。
https://tochi-no.jp/article/detail/889
午前中は先輩実践者との意見交換

「とちぎ農ある暮らし体験交流会」は、農業や田舎暮らしに興味がある人のためのイベント。農ある暮らしを実践している先輩たちとの交流や、農作業体験、お菓子作りなどが行われました。
実践者4名と参加者13名が向き合う形で座り、司会兼ファシリテーターの鹿島田千帆さんの楽しいアナウンスとともに、イベントが始まりました。参加者は、年齢層も広く、一人での参加のほか、友達同士、夫婦、家族連れとさまざま。
主催者の栃木県農村振興課の森島さんによると、トチノに告知を出してすぐに予約が殺到したとのこと。メモをとりながら話を聞く人もあり、参加者の皆さんは先輩実践者の話に熱心に耳を傾けていました。
先輩実践者のお話

林千緒さん(日光市)
平成31年に宇都宮市から日光市に移住。地域おこし協力隊OG。集落支援をしながら、伝統野菜である川俣菜や赤じゃがいもの栽培、民具(岩芝工芸技術)の継承を行っています。

日光市の栗山エリアは山深く、もののけが出てきそうな雰囲気で、人情に厚い場所です。
現在は家庭菜園を大きくしたような規模で、近くの直売所に出せるくらいの量の伝統野菜を育てています。熊追いのおじいさんたちがいるので、その関係で狩猟もやっています。
君島佳弘さん(茂木町)
平成30年に大田原市から茂木町に移住。農家民宿と天然酵母のパン屋「月noco」を営む傍ら、有機農業体験の運営や地域の小学校でのお米作り授業を行っています。

農家民宿とパン屋のほか、棚田で米を作っています。江戸時代の鍬(くわ)を使って作業している関係で、NHKの大河ドラマ「青天を衝け」のサポートも行いました。
1日中自然に触れられて、いい暮らしだと思っています。
倉本祐樹さん(市貝町)
平成31年に宇都宮市から市貝町に移住。有機農家「わたね」として、夫婦で農産物の生産・販売やケータリングサービスを行っています。

季節の露地野菜、在来種の大豆、コーヒーを育てています。
自分で種をまいて育てたものをお弁当や料理に変えて、ケータリングサービスをしています。
市貝町はオーガニックビレッジとして、有機栽培を推進している場所です。
千葉慶章さん(さくら市)
平成31年に神奈川県からさくら市に移住。地域おこし協力隊として農産物直売所「菜っ葉館」勤務を経て、ネギ農家で働きながら、自然薯の栽培もしています。

さくら市内のお米とネギを栽培している農家の従業員として農業をしています。そのほかに、自分でも自然薯を育てています。
虫が苦手で、まだ、騒ぎながら作業しているような状況です(笑)

千葉さんのお話から、農作業と虫の話で盛り上がりました。
葉物野菜にはヨトウガの幼虫がつきやすく、ベテラン農家だと手でつぶして処理する人もいるのだとか。
そのほか、君島さんからはゴマには虫がつきやすい、大きな蛾が出て難儀した、といったエピソードの披露もありました。
また、地域の方たちについての話題になり、70~80代の農家さんたちがみんな元気だということ、農業やその地での暮らしで分からないことがあれば力になってくれるということ、都会とは距離感が違って、濃密な関係性になることなど、それぞれが語りました。
「大先輩の農家さんたちの経験談は、できるだけ聞いたほうがいい」というアドバイスもありました。
農業の高齢化はどこも進んでいて、耕作放棄地になりかけていたり、農機具が放置されていたりといった状況は、これから就農する人にとってはむしろ追い風になる、というのは4地域の皆さん共通の見解でした。
参加者からは質問が

農業と民宿を両立している君島さんに対して「朝から夜まで働くことになり、タイムマネジメントが難しくないくないですか? 民宿のチェックイン、チェックアウトを自動化しているなどの工夫はありますか?」という質問が出ました。

この生活を始めて7年くらいですが、いまだに試行錯誤しています。ゴールデンウィークや夏休み、モビリティリゾートもてぎのイベントなどの時はかなり忙しく、昼間農作業をして、夜に掃除など宿のことをしています。料理やパン、焼き菓子などは妻が担当してくれています。
無理がないように、農業は栽培作物をしぼって、手が回る範囲でやっています。
サラリーマン経験がある千葉さんには、セカンドキャリアで農業を考えている方から収入に関する質問が出ました。

正直言って、毎月固定給がもらえるサラリーマンに比べると厳しいと思います。
私自身は、同じ作物をずっと続けていく自信がなかったのもあって、農家の従業員として収入を得ながら、自分の畑は拡大せずにやっています。
多くの収入を得たいなら、1つの作物にしぼって投資をして、ということになるかと思います。
地元野菜たっぷりの料理を囲んで、にぎやかなランチタイム

ランチは、ろまんちっく村ヴィラ・デ・アグリ内にある和食レストラン「ゆず庵」でした。
この日のための特別定食は、地元の野菜や湯葉を使ったもの。
湯葉のしんじょや、野菜天ぷら、栃木県の郷土料理「しもつかれ」をベースとした汁物に舌鼓を打ちながら、参加者同士の交流を図りました。

午後は畑へ!みんなで農作業にチャレンジ
新里ねぎの畑で草取り体験

農作業体験は、草取りと種まき。
草取りしたのは「新里(にっさと)ねぎ」のほ場です。このねぎは、宇都宮市新里町で江戸時代から育てられてきた在来種の曲がりねぎ。7~9月に、生長したねぎの近くを掘り、根ごと斜めに倒して根元に土をかける「踏み返し」といわれる植え替えを行うことで弓形に曲がったねぎに育てます。
甘さと柔らかさが特徴です。

この日は、おいしいねぎづくりに欠かせない草取り作業をしました。事前にアナウンスしてあったとおりに、長靴と帽子を身につけた参加者と実践者の先輩たちは、畝間に生えた草を鎌で刈り取っていきます。
暑い日の作業は大変ですが、皆さん慣れた様子で時間をかけずにきれいに刈っていました。開始からしばらくすると、あちこちから「終わりました!」という元気な声が。参加者に話を聞くと、家庭菜園や実家の畑などで経験がある方も多いようでした。
ほうれん草のほ場で種まき体験|後日、収穫もできる!


黒マルチ1列分が、今回の参加者の場所。「ほうれん草の種って思っていたより大きい!」「種はどうして赤くなっているんだろう」といった声があがるなど、各自楽しそうに種をまいていきました。
このほうれん草は、後日、生長の様子を写した写真が参加者に送られます。葉が育っていく過程を見守りながら、「収穫の時期にはぜひ畑に来て収穫してください」と案内がありました。体験はその日だけで終わらず、育つ喜びと収穫の楽しみまで続いていきます。

人気パティシエ直伝!みんなで楽しむお菓子作り

この日最後のイベントは、お菓子作り。ほうれん草のスコーンを、「欧風菓子グリンデルベルグ」オーナーシェフの門林秀昭さん指導のもと作りました。
キッチンの作業台は8人までしか入れないため、2組に分かれて作業を行いました。
おやつに食べることの多いスコーンと野菜のほうれん草の組み合わせということで、参加者は興味津々でした。

フードプロセッサーで細かくしたほうれん草と小麦粉などを混ぜ、生地を伸ばして型で抜いて作ります。
普段から料理をしている方が多いのか、粉をふるったり、混ぜ込んだりといった作業を皆さんすんなりこなしていきます。この日最年少の参加者さんは、家族からアドバイスを受けながら一所懸命作っていました。
作業している人以外は、ガラス窓から作業者の様子を見ているのですが、その間、鹿島田さんが実況して、見学者を飽きさせませんでした。

焼きあがったスコーンはまわりがサクサク、中がしっとりで、ほんのりほうれん草の香りと甘味を感じるものでした。
その場で食べられなかった分は持ち帰り。
門林さんからは「ほうれん草の代わりに、にんじんを使ってもいいですよ」とのアドバイスもありました。
参加者からはこんな声が

セカンドキャリアの参考になった
夫婦+四女の3人で参加しました。祖父母の畑を手伝うこともあるので、娘も農作業には親しんでいます。夫婦ともに実家が農家で、セカンドキャリアとして栃木県での就農を考えています。(県外から参加)
農業への関心から参加し、学び多い時間になった
夫婦で参加しました。妻の実家が農家だということもあり、農業に興味があって参加しました。いろいろな情報をいただき、勉強になりました。(県外から参加)
農業のいいこと、悪いこと両方が聞けた
いい面だけでなく悪い面も含めてリアルな農業の話が聞けました。先輩実践者の話を聞いて、これから何をどう進めていくのかイメージできました。(県外から参加)
自然とのふれあいの楽しさを知った
ファシリテーターの鹿島田さんのお話がとてもおもしろかったです。先輩実践者の話を聞いて「自然と触れ合うのは楽しいんだ」と感じました。(県外から参加)
栃木へのUターン後の参考に
実践者との意見交換がとても参考になりました。栃木へ帰ってくることになったら、楽しく農ある生活ができそうです。(県外から参加)
今後もさまざまなイベントを開催!

内容が盛りだくさんのイベントに、参加者の皆さんは大満足!
今後も、栃木県農村振興課主催の催し物が企画される予定です。農業や農ある暮らしに興味がある方は気軽に参加してみてください。
 TOCHINO-トチノ-
TOCHINO-トチノ-